

マーケティングと営業の
成果を変える
ツールとサポートプログラム

※Cloud CIRCUSブランドのSaaSプロダクトの導入アカウント数 2023年12月実績


















Pick up

BtoBの集客・商談創出に
Web制作サービス

印刷会社のための
デジタル支援サービス

toC企業のための
ファン創出・育成サービス

BtoBのマーケ支援
デジマ総合支援サービス
Cloud CIRCUSの主なツール
Webで集客を実現
Webの専門知識がなくてもOK!手厚いサポートで安心してWebサイトを制作・運用できるサービス
BlueMonkey Webサイト制作・更新

- 国産有料CMS 国内シェア3位
- 導入実績2,300社以上
- 継続率99.6%
見込み案件を創出
圧倒的に使いやすいマーケティングオートメーション!ユーザーの行動を可視化し、熱い見込み顧客を見つけることができる
BowNow 見込み顧客化・商談化

- MAツール国内プロバイダシェアNo.1
- 導入実績13,000社以上
- 継続率98.4%
SNSで拡散と顧客体験の向上
SNSキャンペーンやオンラインでの活用にも最適なAR!
新しい顧客体験を提供、満足度向上に繋げる
AR・SNS拡散・顧客体験 LESSAR・COCOAR

- LESSAR導入実績7,500社以上
- COCOAR導入実績7,100社以上
- 有名企業・自治体とのコラボ展開多数
発信・共有を楽に
資料・動画を簡単に配信できる電子ブック作成ツール
PDF等のデータをアップするだけ!
電子ブック・動画共有 ActiBook

- 導入実績17,000社以上
- 3ステップで作成から配信までできる
お得なセットプラン
「業界」と「解決したいこと」に最適化させた2つのプランご用意しています。
通常のプランよりお得にご利用いただけます。


- Webマーケでの商談創出のやり方が分からない
- Webサイト経由の受注がなかなか増えない


- ペーパーレス化が進み収益が落ちている
- デジタルを取り入れた提案をしたいがやり方がわからない
コンサルプラン
カスタマーサクセスプログラムより、更に深い支援をご希望のお客様には、有料のコンサルプランを複数ご用意しています。
お客様のご状況に合わせて、必要なコンサルプランを必要なだけご利用いただけます。


MAツールを使って最短で成果を出すためのコンサルティング支援プラン
<支援する領域>
- ホワイトペーパーの作成を代行し、見込み顧客の獲得を行う
- 関係構築メールの作成を代行し、見込み顧客を見つける
- 見込み顧客を生むメールを作成し、顧客の育成を行う
- 見込み顧客を抽出し、アプローチすべきリードを探す
- 架電対象を選定し、商談獲得するためのアプローチを支援
- できるだけ早く成果を出したい
- ツール活用だけでなく、売上に繋げる支援まで受けたい
- 施策の助言だけでなく、初期の計画から手伝って欲しい



2,100社以上の実績(IT/製造業)・独自メソッド
を基に、クリエイターのいるデジタルマーケティング(デジマ)専門チームが戦略立案から実行まで
伴走します。
SaaS・AIツールを駆使しながら低コストで高い
リターンを継続的に出し続けます。
- マーケティング施策を実行していくリソースが足りない
- 成果が出ていない原因が分からない
導入事例
Cloud CIRCUSを導入したお客様のインタビューを紹介しています。
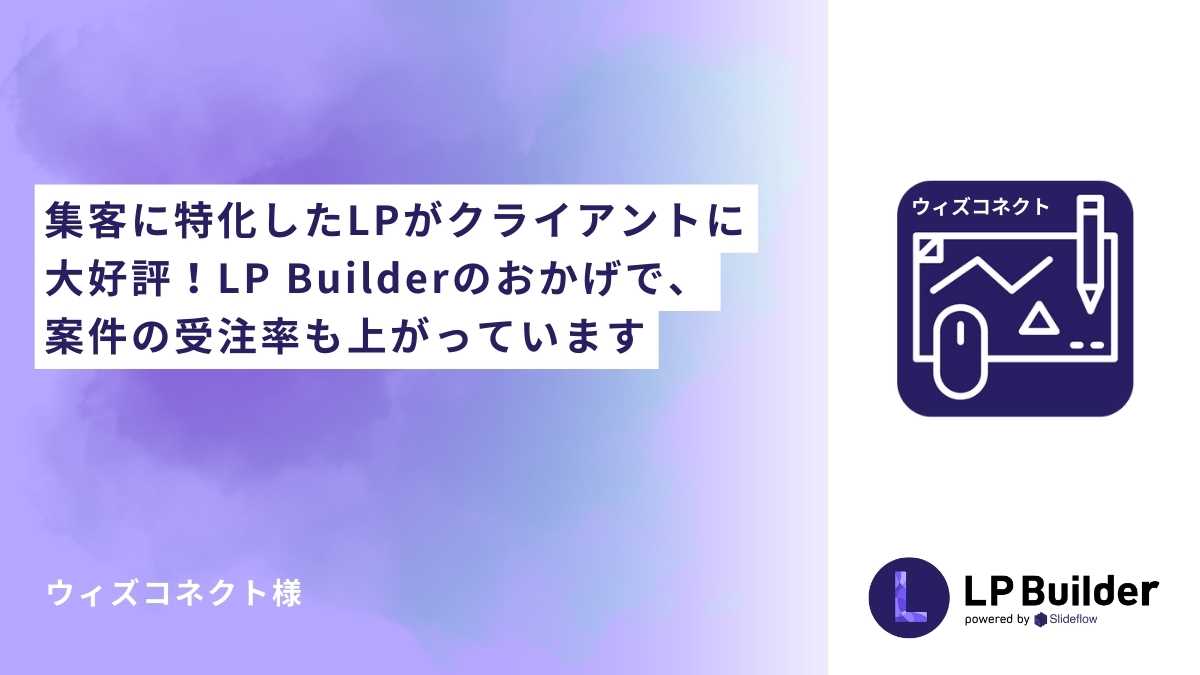
2024/04/19 集客に特化したLPがクライアントに大好評!LP Builderのおかげで、案件の受注率も上がっています|ウィズコネクト様
クラウドサーカス株式会社が提供する、PowerPointやGoogleドキュメントの資料をWebサイトに変換できる「LP Builder」を導入したお客様の事例...
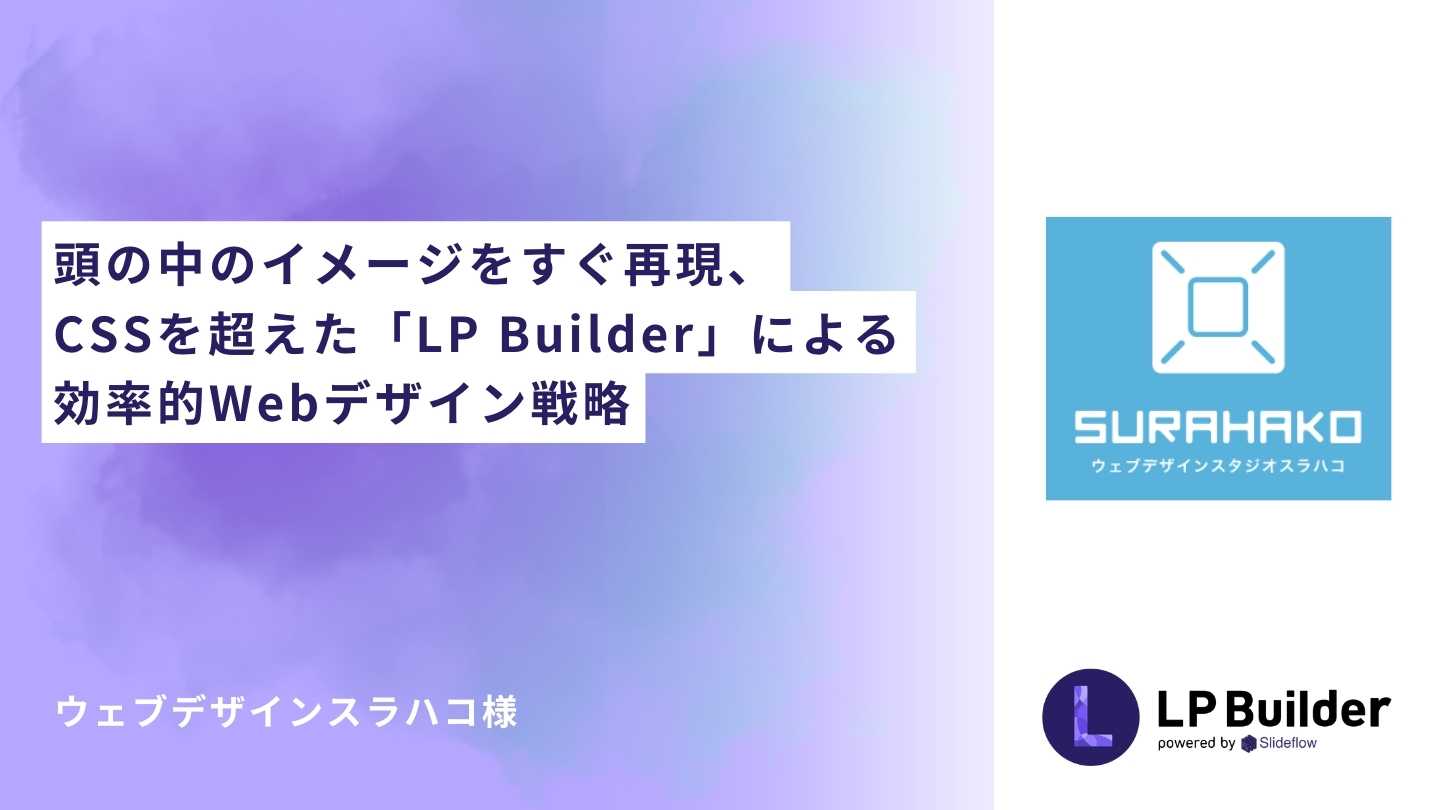
2023/12/25 頭の中のイメージをすぐ再現、CSSを超えた「LP Builder」による効率的Webデザイン戦略|ウェブデザインスタジオ スラハコ 様
頭の中のイメージをすぐ再現、CSSを超えた「LP Builder」による効率的Webデザイン戦略|ウェブデザインスタジオ スラハコ 様 クラウドサーカス株式会社...
業界別に最適なツール・プラン
お役立資料
情報収集や社内共有用にぜひご活用ください
最新情報










